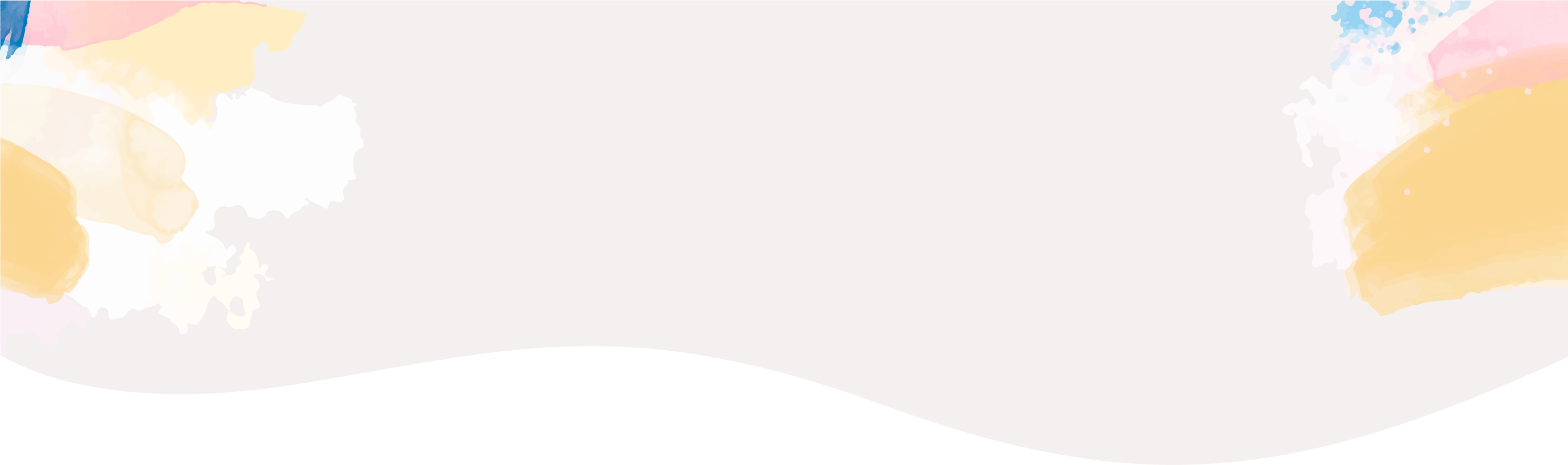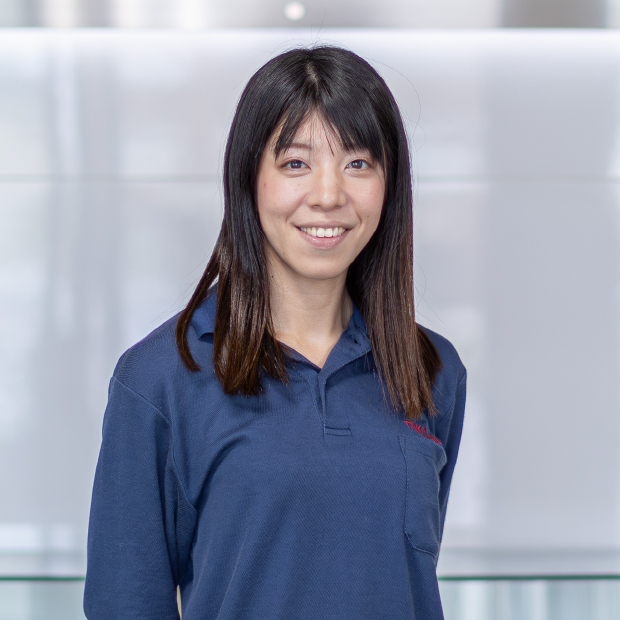モノづくりの全てを見渡せる環境
工学部で機械工学を学んでいたこともあり、「モノづくり」に関わる仕事をしたいと思っていました。一部の工程だけでなく、【ゼロから完成まで】全体を見渡せる、【自分が携わったものが形に】なり実際に動く様子を見届けられる、そんな会社で働きたいと思っていたんです。また、せっかくなら、【スケールの大きなモノづくりに挑戦したい】という想いもありました。そこで自動車業界を中心にいろいろな企業を調べる中で、TAKATSUに出会いました。設備の開発から設計、製作、そしてお客さんの工場で稼働するまで、モノづくりの全体を見渡すことができ、「クルマのボディ生産ライン」という大規模な設備に携われる。【スケールの大きな仕事に挑戦】し、【モノづくりをはじめから終わりまで見届けられる】理想的な環境だと感じました。